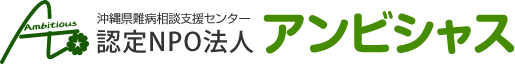- ホーム
- 難病情報
- 難病情報誌 アンビシャス
- 難病情報誌 アンビシャス 279号
難病情報誌 アンビシャス 279号
最終更新日:2025年08月04日

表紙は語る
障害があってもあきらめない
田中 晶子(たなか あきこ)さん
強直性脊椎炎
こんにちは!田中晶子と申します。私は強直性脊椎炎という骨の難病を患っています。現在、宮崎で社会保険労務士をしています。障がいと共に生きる暮らしをサポートする社労士を目指しています。主に障害年金の代理請求や審査請求等、障害年金に係る業務をしています。その他、仕事と病気の両立支援や働き方改革・ハラスメント対策等にも携わっております。障害年金のご相談をされる方の、疾病の割合としては精神疾患の方が多いですが、同じ病気の方や他の難病の方からもご相談をうける事もあります。障害年金を受給する事が、今後の治療や人生設計に前向きになれるきっかけになればいいと思いながらサポートをしています。
強直性脊椎炎とは、脊椎や骨盤の仙腸関節に炎症が引き起こされる病気です。免疫作用が過剰にはたらいて自身の組織などを攻撃してしまう〝自己免疫疾患〟であると言われています。強直性脊椎炎は、平成27年7月から指定難病となり、症状が該当すると、医療費の助成が得られるようになりました。
この病気は、骨が炎症を起こして、痛みが強いというのが特徴ですが、私の場合は、ほとんど痛みや自覚症状はありませんでした。ただ、20歳を過ぎた頃から、徐々に関節の可動域が狭くなってきました。横断歩道を急ぐ時、上手く走れなくなり、何でだろう?と思っていました。その後も、徐々に背骨が変形して姿勢が前かがみになり、歩くとき、上手く前を向けなくなってきました。何度か整形外科を受診しましたが、どこにいっても原因はわかりませんでした。かなり変形が進んでから、地元の大学病院を受診して、そこで初めて「強直性脊椎炎」と診断されました。病名を告げられた時は、ショックを受けたというよりも「ああやっぱり、体質ではなかったんだ。」と何処か納得したのを覚えています。
診断がついたものの、特に治療法はなく、背骨の変形は進んでいきました。特に、頸椎が曲がって前を見て歩くのが難しくなってしまいました。まだ、30代なのに、今後、どうなっていくのだろうか?と不安を感じていました。色々調べてみて、地元の大学病院では背骨の手術はできないとの事でしたので、東京の大学病院で手術する事にしました。2016年6月に脊柱を固定する手術をしました。
その後、本格的に社労士として開業して1年程たった、2018年の4月頃から股関節が痛くなり、7月には、ほとんど歩けなくなってしまいました。家の中でも、常に両手で杖を支えに歩くような状態でした。外出先では車椅子を借りていました。その頃、1度目の手術で固定されていない背骨の下の方が曲がってきていて、再度の背骨の手術を検討していました。しかし、歩けないので、背骨の手術は後回しになり、8月に緊急で右股関節の手術をしました。が、それでも歩けるようになりませんでした。その後、左の股関節も急速に悪化し、12月に左股関節を手術しました。ようやく歩けるようになったのは、2018年暮れのことでした。その後、2019年2月に、2回目の背骨の手術をして、脊柱を骨盤から固定しました。合計1年程、東京の大学病院に入退院を繰り返す事になりました。
指定難病で医療費助成の対象になると、高額療養費よりもかなり低額に自己負担額を抑えられるので、入院した場合や高額な治療が継続的に続く場合は非常に助かりました。また、その間に、障害者手帳を取得し、障害年金も請求して2級に認定されました。
2度目の背骨の手術後は、身長も戻り視界も変わりました。今まで、歩いている時、常に下しか見えていませんでしたが、退院後に初めて駅を歩いた時、天井を感じたのが新鮮でした。合計4回の手術で、まるで、サイボーグのような体になってしまいましたが、6年経過した現在も痛みもなく歩けています。現在は年に1度、東京に定期健診に行っています。手術してくださった先生方をはじめ、大学病院の整形外科チームの皆様には大変感謝しております。
さて、表紙の写真についてですが、今年の5月に高知県・南国市の尾長鶏センターに、オナガドリを見にいった時のものです。南国市には高知竜馬空港があり、朝ドラの「あんぱん」の「後免駅」もあります。オナガドリは尾の長さが4.5メートルはある鶏で、国の特別天然記念物に指定されています。昔から土佐で飼育されていて、明治以降は様々な記録が残っているそうです。ギネスには、10メートル60センチが記録されているそうです。オナガドリは野生に生息している品種ではなく、何世代も品種改良を重ねて、人の手で大切に育てながら保存されている鶏です。オナガドリの飼育は、尾を丁寧に扱う必要があり、非常に難しいそうです。最近は、後継者がおらず、一般に見られる機会が少なくなってきているそうです。センターの方にお話を伺いながら、ゆっくりオナガドリを見る事ができました。オナガドリ以外にも、まだまだ美しい日本鶏がいます。鶏が大好きなのでいろいろな鶏に出会いたいと思います。
語者プロフィール
田中 晶子(たなか あきこ)さん
1980年生 宮崎市出身
【いつか行きたい所】エジプトのピラミッド
【好きな音楽】B'z
2025年6月の報告あれこれ
沖縄県難病患者人工呼吸器用外部バッテリー等貸与事業開始
今年度も、6月1日から非常用電源確保事業の受付が開始され、7月末までの受付期間となるので、この報告を読まれる頃には受付は終了しています。
この事業において照喜名は保健所の保健師に同行し、在宅で人工呼吸器を装着している指定難病の方や小児慢性の方の自宅を訪問し、事業の概要や防災について説明させていただいています。事業の概要から申請書の書き方、機種の選び方に加え、安否確認の方法や家具の固定などの防災についても説明しています。この事業の対象となる方は人工呼吸器を装着していて、容易に動けないため在宅避難が中心になってくるのですが、在宅で過ごすためには備蓄や正しい知識も必要になってきます。
中部保健所での災害対策講話
4日に行われた災害対策講話には中部保健所の難病担当の方、異動で今年度から難病担当になった方が参加されました。この講話は、県の貸与事業の概要、進め方、発電機と蓄電池の違いなどに加え、実際に機器を触って動かして支援対象となる難病患者や小児慢性の方々のスキルアップになることを期待して実施されました。
コミュニケーション支援機器講座
21日、ITサポート沖縄とアンビシャスの共催で、コミュニケーション支援機器講座が、ともかぜ振興会館にて開催されました。講師は、アクセスエール株式会社代表 松尾光晴氏でファインチャットの開発者です。定期的に宮古島や沖縄県に来ていただいて感謝しています。参加者は支援者の中でもリハビリの専門職が多く、患者当事者の参加もありました。コミュニケーション支援機器を使用するうえで重要なのは、それを操作するスイッチの相性となります。アンビシャスとITサポート沖縄では、各種スイッチの在庫を持っていますので、その方の病状の進行や動かせる状態に合わせてお試しいただけます。速やかな導入が患者の支援になります。
6月のご寄付
6月12日株式会社大央ハウジング様の本社において、寄付金の贈呈式を催していただきご厚志を受領させていただきました。
代表の前盛様は「地域社会への貢献」という言葉で表現されていましたが、実際に実行することは、容易いことではありません。それも永年に亘って継続することは、更に難しいことだと思います。
また、全保連株式会社様からも高額のご寄付をいただきました。営業の成果のご寄付は、社員の皆様のご理解があって実現するものであり、背景には沢山の方々の想いがあって実現するものだと思います。
皆様からのご寄付は、その意思に沿うようアンビシャスの難病支援活動に活用させていただきます。ご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
アンビシャスメモ
保健所スケジュール
各保健所、今月の予定はございません。
【北部保健所】 Tel:0980-52-2704
【中部保健所】 Tel:098-938-9883
【南部保健所】 Tel:098-889-6945
【那覇市保健所】 Tel:098-853-7962
【宮古保健所】 Tel:0980-72-8447
【八重山保健所】 Tel:0980-82-3241
令和7年度【10月開講】障がい者委託訓練生募集
【募集期間:令和7年8月1日(金)~25日(月)】
【訓練期間:令和7年10月1日(水)~令和7年12月26日(金)】(3ヵ月間)
具志川職業能力開発校管轄
コース名:CADオペレーター養成科(知識)
定員:4名
管轄校:具志川校
募集対象:身体【上肢・下肢(車いすの方要相談)・聴覚(要相談)・内部障害】、精神、発達、その他(高次脳機能障害、難病)
訓練場所:沖縄市
委託先:有限会社ビーンズ
コース名:リネン類クリーニング科
定員:1名
管轄校:具志川校
募集対象:知的障害、精神障害、発達障害、その他(高次脳機能障害・難病)
訓練場所:中城村
委託先:沖縄綿久寝具株式会社(中城工場)
※受講料無料(但し保険料等は自己負担)テキスト代・検定料があるコースは別途自己負担。
【お問合せ先】具志川職業能力開発校 TEL:098-973-6680
2025年度 難病医療相談会
難病医療相談会では、難病の詳しい説明や治療・療養について、各疾患の専門医による個別相談(お一人30分間)を無料で受けることが出来ます。
※各疾患とも定員は4組です。定員を超えた場合はキャンセル待ちとさせていただきますのでご了承ください。
※予約時に相談員が相談内容や現在の治療についてお伺いします。おくすり手帳等を手元にまとめご連絡ください。
【疾患】肝臓系疾患/自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎など
【担当医】前城 達次先生(琉球大学病院)
【日程】8月9日(土)16時~18時
【疾患】消化器系疾患/クローン病、潰瘍性大腸炎など
【担当医】金城 福則先生(浦添総合病院)
【日程】8月16日(土)10時~12時 チラシ案内の日時より変更
【疾患】皮膚系疾患/水疱症(天疱瘡・類天疱瘡・先天性)・神経線維腫症など
【担当医】山口 さやか先生(琉球大学病院)
【日程】8月16日(土)13時~15時
【疾患】神経系疾患/パーキンソン病・重症筋無力症・多発性硬化症など
【担当医】渡嘉敷 崇先生(沖縄病院)
【日程】8月22日(金)14時~16時
【開催場所】アンビシャス事務所(那覇市牧志3-24-29グレイスハイム喜納2-1階)
【相談方法】対面またはオンライン(Zoom)
【お申込・お問合せ】
沖縄県難病相談支援センター(認定NPO法人アンビシャス)
Tel:098-951-0567(平日10時~17時)
2025 「難病と診断されたときに役立つしおり」コラボ企画 難病ワークショップ
ヘルスリテラシーについてご存じですか?ヘルスリテラシーとは、医療に関する正しい情報を入手し、正しく理解して、評価、意思決定をする力のことです。この機会に、納得して治療を選択するために大事なことを一緒に学びませんか?!
【演題】難病とヘルスリテラシーについて
【講師】聖路加国際大学大学院看護学研究科教授中山 和弘先生
【日時】8月20日(水)14時~16時
【会場】沖縄県総合福祉センター東棟501教室またはZoom
【対象】難病患者様ご本人、ご家族、支援者、興味のある方
【申込み】こちらの申込フォームよりお申込みください。申込み締切は、8月15日(金)です。
2025年度 難病患者特別講習
『難病とストレスとのつきあい方~マインドフルネス瞑想を取り入れて~』
難病を抱えていても、病気によるストレス、病気以外のストレスに上手く対処できるよう、一緒に対処法を学んでみませんか?
本講習は、心を安定させて、必要な治療に積極的に取り組めるよう、生活の質を向上させることが目的です。
日程 ※各日14時~16時
1回目:10月9日(木)
2回目:10月30日(木)
3回目:11月20日(木)
4回目:12月11日(木)
【講師】沖縄国際大学総合文化学部 教授・公認心理師上田幸彦先生
【対象】患者様ご本人で、4回全て参加可能な方。
【定員】先着4名(申込締切:8月31日)
【会場】オンライン(Zoom)(※オンラインに不安のある方は、アンビシャス事務所での受講も可能です。ご相談ください。)
【お問合せ・主催】
沖縄県難病相談支援センター(認定NPO法人アンビシャス)
電話:098-951-0567(平日10時~17時)
【申込み】こちらの申込フォームよりお申込みください。
こころの現場から
精神科へ、どのように繋げるか
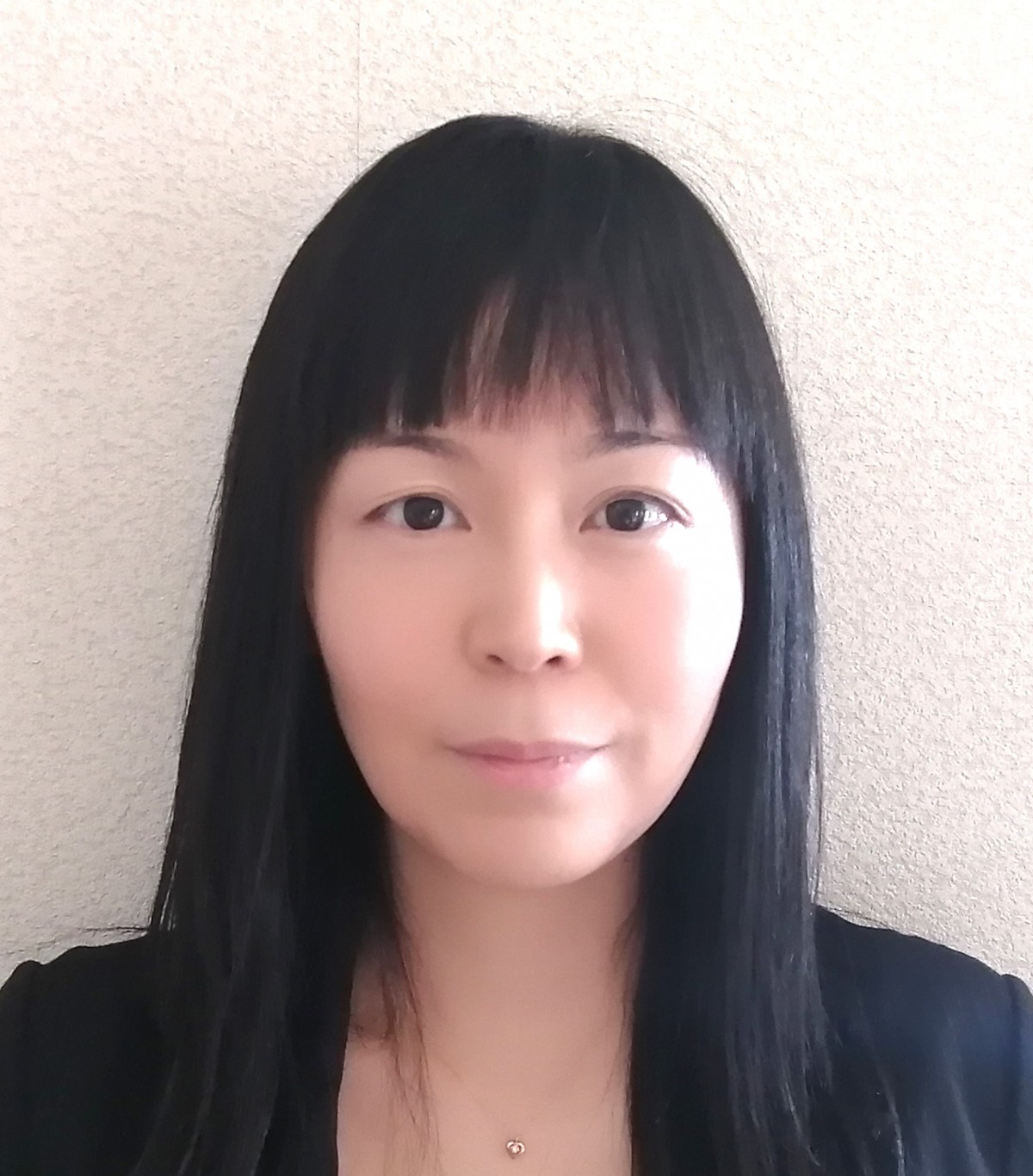
臨床心理士 鎌田 依里(かまだ えり)
前の月では、精神科受診に対しての敷居が低くなっていると書きました。確かにその通りの現実があります。しかし、精神疾患の病理が重篤な人ほど、自分が病気だとは思わないので受診しません(これは病識がないといいます)。周囲の人が困っているにもかかわらず、当の本人は困っていない(=病識がない)ので、精神科への受診をしようとはせず、未治療のまま状態は改善せずに継続していくのです。
例えば、クライエント(相談に来た人)と話をしていて、クライエントが「私はスピリチュアルに興味があって、実は霊が見えるのです…」等と話し始めたとしましょう。そうするとこちらは〈あれ?〉と気が付くわけです。しかしそのまま〈うんうん〉と傾聴していくと、クライエントは部屋の中の虚空にせわしなく視線を移しソワソワとし始めます。こちらは何か見えているのかなと思いつつ〈どうされましたか?〉と問うと「この土地は昔からあまりよくない場所なんですよ。それに相談に来る人たちが悪いモノを連れてくるし。この部屋には5人いますね…」等と続けます。すると、こちらは〈この人は精神科での投薬治療が必要だな。傾聴する時間が長くなってはいけないな〉と確信するわけです。そのような話をしているうちに「色々なものが見え色々なものが聞こえる」という話も具体的に出てくるのです。
本人は病識がありませんし、ここに悩みを相談しに来ているので、それ以外の精神科には通常行きたがりません。しかし、何かしらの不安を抱えているから相談に来ているので、例えば〈その不安や寝つきの悪さ等を改善するために薬の力に頼ってはどうか〉等と助言し精神科への受診を推奨するのが一つの方法です。
つぶやきチャンプルー
ヘルスリテラシーって何?

著:照喜名通
巷では、新聞やテレビ、インターネットなどで毎日のように健康食品のコマーシャルが流れてきます。個人の体験という注意書きが小さく書かれていますが、それが本当に自分に合うのかわからないけども、何かしらの期待を持って購入していると考えます。
「食べ物を床に落としてもすぐに取ったら大丈夫。」というような、いわゆる3秒ルールというのがあって、落ちたとしても3秒以内に拾うことができれば食べても大丈夫という非科学的な振る舞いをするわけです。微かな記憶ですが、昔、「北の国から」のドラマの中で五郎さん(田中邦衛)が新吉(ガッツ石松)から「梅干しを丸ごと飲んだら身体に良い」と教えられ飲んだけど、数日後腹痛がして病院でレントゲンを撮ったら、梅干しの種が数個胃の中入っていたというエピソードがありました。笑ってしまいますが、手軽に食料品で身体が良くなるのならチャレンジしたくなるのでしょう。また、体調が悪いと何かにすがりたくなる気持ちも分かります。8月は「難病とヘルスリテラシーについて」の勉強会を予定しています。聖路加国際大学大学院看護研究科の中山和弘教授をお招きして講話があります。(詳しくは5ページを参照ください)日本は医療の皆保険が充実しており、すぐに病院にいけるので、諸外国と比べヘルスリテラシーが低いようです。健康を維持するため、正しい情報を入手してちゃんと活用できるようにしていけば、自分も家族も健康に近づくと思います。
シリーズ 「患者学」第124回
新しく開発された薬は安全か?
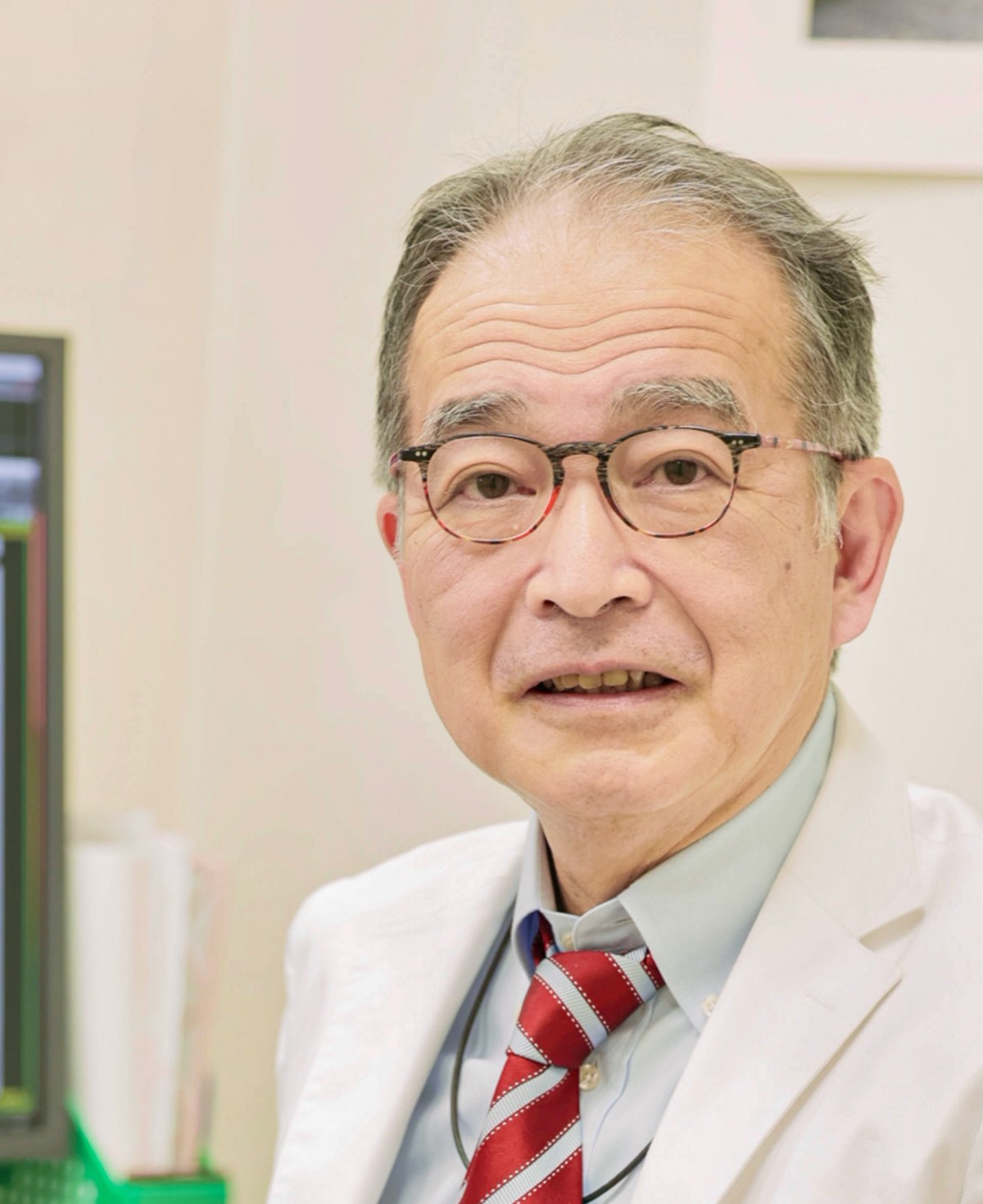
慶應義塾大学 名誉教授 加藤 眞三著
おそらく難病を抱えている患者の皆さんは、夢の新薬が開発されることを待ち望んでいることでしょう。ところが残念ながら、新薬が創られるためには膨大な費用と長期間の研究開発が必要であり、一朝一夕に新薬が誕生することはありません。開発された薬はある程度限定れた患者さんの中で臨床試験が行われ、その効果や副作用がチェックされ、承認され、実際の販売はさらに遅れるのです。
新薬が販売された後に、もう一つ関門があります。市販後に思わぬ副作用が出てくる場合があるのです。例えば次の様な例があります。
1979年、ヤマサ醤油がソリブジンを新規に合成し、ヘルペスウイルスへの抗ウイルス作用を確認し、1985年から帯状疱疹薬として開発され、1993年7月に承認されました。ここまでに14年が経過しています。同年9月に抗ウイルス剤ソリブジンとして発売されましたが、発売後1ヶ月足らずでフルオロウラシル系抗癌剤との併用で重篤な副作用が発生しました。9月21日に第一症例が、10月6日に第2、第3例が報告され、厚生省は相互作用に関する注意を喚起する文書が配布されました。10月12日、ソリブジンと5-FU系薬剤との相互作用による死亡3例を含む7例の重篤な副作用発現が公表されました。11月1日企業による自主回収が開始され、最終的に死亡例が15例あったのです。
この事件は、製薬会社、マスコミ、厚労省の対応などに関して多くの教訓が含まれています。患者さんにとって一番大切な教訓は、「臨床試験(治験)によって承認された薬でも、市販後に多くの人に使われることになると、思わぬ副作用が出てくる可能性がある」ことです。
ソリブジンはヘルペスウイルスに対する抗ウイルス薬であり、抗がん剤で免疫力の落ちた人ではヘルペスが発症することは稀ではありません。そのために、この薬が抗がん剤と併用されることになることはある程度予想できました。しかし、治験は、通常副作用が出そうな患者さんをなるべく避けて行われます。そして、市販されてしまうと、治験では対象とならなかったような人にも使われてしまうのです。
実は、この薬は動物実験でも抗がん剤との併用の問題が指摘されていました。しかも、治験中に抗がん剤との併用で副作用の出た患者さんが一人いたため、市販開始時には「フルオロウラシル系の抗がん剤との併用は避けること」との注意が相互作用の欄に記載されていたのですが、気付かれなかったのです。
市販後に重篤な副作用が出た例として、マロチレートという薬で肝臓でのアルブミンの産生を促す薬もあります。アルブミンは肝臓病の予後(経過)にも大きく影響する物質であり、アルブミン産生を増やすことには大きなメリットがありました。治験は慢性肝炎や代償性(軽症)肝硬変を対象に行われ、良い成績をおさめ、認可されました。
しかし、市販後、アルブミンが低い症例として非代償性(進行した)肝硬変患者が治療対象になり、肝不全例を多く発症したのです。アルブミンの低い肝硬変患者は肝臓の予備能も低く、危険性が高かったのです。
このように、薬は承認後にも、市販後6ヶ月間の再調査で重篤な副作用が明らかになることが度々あります。そのため、わたしは、特別の急ぐ事情がない限り、新薬の使用を半年は避けることが賢明だと考えていますし、患者さんも新薬に飛びつかないという注意が必要だと思います。
- 慶応義塾大学看護医療学部
名誉教授 加藤 眞三 - 慶應義塾大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所研究員。
患者と医療者の協働関係を作り上げることをテーマに公開講座「患者学」や著作 等を通じ、患者も自ら積極的に医療に参加する啓発活動に取り組む。
加藤先生の YouTube配信中です!
「Dr.シンゾウの市民のための健幸教室」
加藤先生の最新書籍:いのちをケアする医療
出版社:春秋社
患者団体からのおたより
沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄)宮古支部eye(愛)の会より
催しのご案内
沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄)宮古支部eye(愛)の会では、協賛企業のメガネ1番様のご協力を得て、次の要領で視覚障がい者のための機器及び新商品の拡大読書器も展示します。
また、沖視協の主催で、同協会の訓練士による歩行訓練の催しが隣接会場で予定されています。
【内容】視覚障がい者のための機器展示 訓練士による歩行訓練を受けられます。
【対象】見づらい・見えにくい・見えない方(疾患は問いません)
【日時】8月20日(水)10時~15時
【参加費】無料
【会場】宮古島市社会福祉協議会 平良支所
【主催】沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄)宮古支部 eye(愛)の会
【協賛】メガネ1番
【協力】宮古島市社会福祉協議会 平良支所
【申込み】不要/当日お気軽にお越しください
【連絡先】沖縄県網膜色素変性症協会 宮古部会(伊良波)090-8294-6174
※沖視協の訓練士による歩行訓練については、次の連絡先にご連絡ください。
(沖視協)098-863-2997
全国膠原病友の会 沖縄県支部より
医療講演会のご報告
令和7年6月28日(土)那覇市牧志駅前ほしぞら公民館「ホール」にて「膠原病と共にあること~セルフケアと支え合いを考える~」のテーマで豊⾒城中央病院 ⿇酔科部⻑・緩和ケア内科 全⼈的痛みセンター⻑ 笹良剛史先⽣のご講演がありました。
笹良先生は、がんの患者さんや慢性的な痛みを抱えた患者さんの心と身体を一緒に診てくださる先生です。
がんや難病と呼ばれる疾患は、今では患者さんも長生きするようになり、いかに病と共に生きて行くか?が大切になってきます。長い治療・療養生活では痛みや心の苦しさと向き合う事が多く、苦しみ痛みからストレスとなり、そのストレスが自己を攻撃し、炎症を起こすこともわかってきたそうです。そのことから治療はお薬だけではなく、そのストレスとどう付き合うか?うまく付き合う事で病気にも良い影響がでる。その方法を教えてくださいました。「マインドフルネス・セルフコンパッション」という方法だそうです。
人間は「今、ここ」以外を考えたとき、ストレスが発生する(過去・未来を思う事)ため、日頃から「今、ここ」に意識する訓練を行って欲しいとおっしゃいました。痛みや苦しみにあってパニックになった時こそ「今、ここ」に集中する「自分の呼吸」にただ意識をする。
そして「慈愛の心」で自分を慈しんで欲しいとメッセージを頂き、自分を慈しむワークを参加者全員で行いました。自身の手で優しく自らを包み「私が、幸せでありますように。私が健やかでありますように…」肩の力がすぅーっと抜けていくのを感じました。笹良先生の温かさをいっぱい頂き、講演会は終了いたしました。
皆さまが「幸せ・健やか」でありますように…
今月のおくすり箱
白い湿布と茶色の湿布
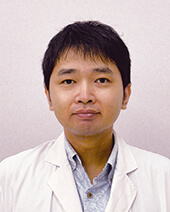
沖縄県薬剤師会 宮里 威一郎
湿布についてはよく「白いのが良い」のように色で言われる方がいらっしゃいます。実際同じ成分でも白いのと茶色のが製造されている場合もあります。これらはどう違うのでしょうか?
白い湿布は「パップ剤」とも言い、白い不織布に厚手の膏体(薬の成分)が塗られたものです。水分を多く含み、患部がひんやりします。厚みがあるので、貼るときに扱いやすく、ぐちゃっとなりにくいです。粘着力がやや弱く、厚みのために服などにひっかかりやすいため、はがれてしまいやすい面はありますが、言い換えれば、はがすときに痛くなりにくいとも言えます。
茶色の湿布は「テープ剤」とも言い、茶色の下地(不織布やフィルムなど)に膏体が薄く塗られたものです。見えるところに貼っていても目立ちません。粘着力が良く、曲げ伸ばしする部位でもはがれにくい特徴があります。その分、はがすときに苦労するのですが、お風呂などでシャワーで濡らしたり、肌が引っ張られないように抑えると剥がすときの痛みを軽減できます。
ご自身の使用状況にあったものがどちらなのか、医師や薬剤師と相談して選びましょう。
アンビシャス広場
~エッセイ~ 「はじめまして」 眞榮田 純義さん(ALS)
皆さんはじめまして。8月号からエッセイの執筆することになりました。眞榮田純義(マエダマサヨシ)と申します。よろしくお願いいたします。
今回、初回の投稿となりますので簡単に自己紹介させていただきます。
糸満市出身で現在は南城市に住んでいます。1994年生まれで今年31歳になります。仕事は訪問看護ステーションの代表取締役、そして日本ALS協会沖縄県支部支部長を務めております。
そして私の疾患は、ALS(筋萎縮性側索硬化症)です。私が初めて体の異変を感じたのは、2021年2月ごろでした。はじめは利き手の右手親指から症状が現れました。最初は腱鞘炎かと思うほどだったので様子を見ていましたがだんだんと足の方にも症状は現れ、何もないところでつまずくようになりました。そして沖縄病院で検査入院をし、2022年4月にALSと診断を受けました。
ALS発症当時はまだ26歳で、診断を受けたのも27歳の年でした。この病気では20代の発症も珍しく、診断当初は病気のこと、制度のことをふくめて情報を取るのにとても苦労しました。
そういった経験を踏まえて、このエッセイ記事やALS協会の支部として患者やご家族や周りの支援者の方々のためにも頑張っていきたいと思います。周りの方々のサポートを受けながら、私も精一杯生きていこうと思います。
お勧め映画/DVD情報
1)ワン・ザ・ウーマン 2021年
記憶喪失ものの韓流ドラマ。ほとんど韓流ドラマを見ていない私でも面白く引き込まれたロマンティック・アクションコメディ。
2)キル・イット~巡り会うふたり~ 2019年
幼い頃の記憶を失い、殺し屋に育てられた青年と殺人事件を追う女性刑事を描いた韓流ドラマ。
3)2ハート/命という名の贈りもの 2020年
2組のカップル、二つのストーリーと愛のストーリーで実話をもとにした作品。
4)いつかの君にもわかること 2020年
不治の病で余命わずかなシングルファザーが、4歳の我が子に出来ることは…こちらも、実話を元に作られた作品。
★渡久地 優子{進行性骨化性線維異形成症(FOP)}★
今月の占い
- 牡羊座 3/21-4/19
体調管理に気をつけて
☆リフレッシュ法:料理 - 牡牛座 4/20-5/20
笑顔で場を明るく
☆リフレッシュ法:読書 - 双子座 5/21-6/21
何事も落ち着いて
☆リフレッシュ法:散歩 - 蟹座 6/22-7/22
助言は受け入れて
☆リフレッシュ法:掃除 - 獅子座 7/23-8/22
挨拶は忘れずに
☆リフレッシュ法:歌唱 - 乙女座 8/23-9/22
美味しい物で栄養を
☆リフレッシュ法:飲食 - 天秤座 9/23-10/23
何もしない時間も大事
☆リフレッシュ法:睡眠 - 蠍座 10/24-11/21
ありのままの自分で
☆リフレッシュ法:ドライブ - 射手座 11/22-12/21
気配りと思いやり
☆リフレッシュ法:談笑 - 山羊座 12/22-1/19
言葉遣いは慎重に
☆リフレッシュ法:スキンケア - 水瓶座 1/20-2/18
噂話や愚痴に注意
☆リフレッシュ法:断捨離 - 魚座 2/19-3/20
早寝早起きで健康体
☆リフレッシュ法:DVD・TV鑑賞
編集後記
今月の「表紙は語る」にご寄稿いただいたのは、強直性脊椎炎を抱えている田中晶子さんの体験談です。社会保険労務士のお仕事をされていて、主に障害年金を取り扱い、手続きに困った人の障害年金受給のお手伝いをすることで、前向きな人生のきっかけになれればと考えていらっしゃるホスピタリティの高い方です。
記事の中で印象的なのは、オナガドリと一緒に映った写真です。この会報誌がきっかけとなり、田中さんの好きな鶏との出会いが増えるといいですね。
今月号の「6月の報告あれこれ」のコーナーでは、行事が多くあり、新しい年度の始まりを感じています。保健所では指定難病受給者証の更新月になっています。手続きは早めにしたいものです。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、先月号より最終ページの協賛広告欄に1法人が新たに追加になっています。皆様に支えられてアンビシャスは、活動させていただいていますことを改めて感謝申し上げます。
季節は夏本番、台風は8月、9月が年間で沖縄接近が統計上多い月となっています。日頃からの備えを心掛けておきたいです。
文 照喜名 通
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.