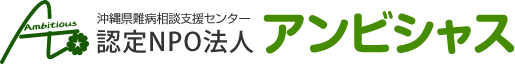- ホーム
- 難病情報
- 難病情報誌 アンビシャス
- 難病情報誌 アンビシャス 280号
難病情報誌 アンビシャス 280号
最終更新日:2025年09月01日

表紙は語る
この病気を次世代へ引き継がせないために
姉:泉川 チズ子(いずみかわ ちずこ)さん
妹:仲村 けい子(なかむら けいこ)さん
沖縄型神経原性筋萎縮症
自己紹介をお願い致します。
姉:初めまして、泉川チズ子と申します。那覇で生まれ育ち、20歳前に恩納村に嫁ぎ家族にも恵まれましたが、残念なことに17年ほど前に夫を亡くして現在は独り身です。兄妹6人おりますが、4人がこの病気を発症しており、30~40代になると、下の姉妹が兄姉を追うように発症、ほぼ段階的に同様に進行していきます。私もそのような中、仕事に子育て、孫たちの子守りと懸命に生きてきました。これから先も、病気に立ち向かう気持ちを維持し、日々薬の研究開発に尽力されている研究者の先生方に惜しみなく協力していきたいと思います。
妹:仲村けい子と申します。泉川のすぐ下の妹です。兄、姉の前向きな生き方を見ているので、自分のお手本にもなっています。
この病気が発症して生活は変わりましたか?
姉:私達は3カ月ごとにリハビリ入院をしています。
妹:ひと月の入院期間は家族にも迷惑をかけますが、その間の姉との時間もいとおしく感じます。姉がシーパップを始めてからは夜の訪問看護が入ることになり、以前のように電話での楽しみができなくなりました。
姉:私は1人暮らしなので「ちょっと危ないかな」と思うことがあったら、翌日には直します。例えばベッドのリモコンを落として拾えない状態が朝まで続いたら紐をつけるとか、飲み物はフォルダーをつけるとか、痰の吸引なども自分でできるように工夫しています。症状が進行してきているので、いろいろ考えますね。介護の手を借りたら楽でしょうが、それに慣れてしまうと必要以上に介護頼みになってしまうので、自分でできることは自分でやろうと常々考えています。
妹:私もこの先を考え、前倒しで電動車椅子を準備してあります。ひと頃に比べ、今はだいぶ歩行器のお世話になっておりますが、自分で歩ける間は自分でと思う反面、転倒したときのことを思うと無理は禁物です。幸いにも孫の手よろしく小5の孫の手に助けられています。子供ながらに日ごろお世話するなかで、要領を得てくるというか、家族に障害者や高齢者の方がいることで、思いやる気持ちの発育度に違いがあるのかと思ったりします。
姉:小学校の福祉教育で「どうやったら泉川さんが、食べやすいか。この飲み物が飲みやすいか」と質問したところ「僕が食べさせてあげる」と答えた子がいました。その細やかな気配りにとても感慨深い思いをしました。無垢(むく)な子供らに他人を思いやる気持ちと、困った人がいたら進んで協力することの大切さを教え導くことも、私たち障害者の役割であり、福祉教育の一環でもあるように思います。
妹:「障害者なので」という内向きな考え方ではなく、誰かに多少なりとも影響を与えられるような前向きな考え方が肝心だということですね。
6月号から希の会の交流会案内を会報誌でご案内しています。詳しく教えてください。
妹:コロナ前はHALの業者の方が毎週データを取っていましたが、コロナ禍で集会が思うようにできなくなり、初代会長の我如古さんが体調を崩してからは我如古さんの自宅で集会をするようになりました。
姉:今この沖縄型研究の要である谷口雅彦先生(聖マリア病院院長 福岡在)をトップに、研究者の先生方が病気の解明に向け頑張っておられます。会合も、遠方の先生方が多数を占めているにもかかわらず地元沖縄で開いてくださり、本当に感謝に絶えません。また新会員の皆さんが携帯等の操作に長け、谷口先生からの助言や提言を滞りなくまとめてくださり頼もしい限りです。他に会の情報発信のスピード化の為Facebookやホームページを作成中です。
妹:会の運営にはお金が必要なので、募金に応募するのですが、書類づくりも結構な仕事になります。願わくば当選して欲しいのですが、もし落選しても挑戦し続けるつもりです。私たち患者は後々動けなくてなっていくのですが、この忌(い)むべき病がどれほど残酷なものであるか、多くの皆様に病気の実態を啓発していかなければならない強い思いがあります。
姉:希の会は今年の10月で11年になります。先生方の意見もお聞きしたいということで、先生方の昼休みに合わせて交流の場を設けています。若い子は、ロゴマークやキーホルダーを作ったりしています。県外や海外に在住の方もいらっしゃるので、世界に向けて情報発信もしております。今、本会の登録者数は25名です。しかし半数の方は不調を訴え集会に参加できていません。病状の進行度が早いことと、参加したいのだが介助者と調整が上手くいかないことなどが要因にあげられます。その間、亡くなった方もおられます。11年の時を経て参加者の顔ぶれもだいぶ変わりました。これからのこと「どうにかしなければ」と思案しております。沖縄病院におかれては、主治医の藤崎先生が公私にわたり頑張っておられることを特筆するとともに心から感謝申し上げます。
これからの目標について教えてください。
姉:私の目標は85歳まではいきましょうってことです。手も足も動けなくなって動けるのは口だけになって、それで生きてるの?みたいにみんな笑うけど「口が聞ければいいんじゃないの」って思います。
妹:私はリハビリです。5月の入院のときHALをやってきましたが、そのお陰で退院してから転ぶことがないですね。その前は何回も転んでいました。やりすぎもいけませんが、椅子から立てるうちはHALのリハビリをしたいです。
姉:ゆっくりゆっくりね。私はやれることはやります。
妹:冒頭でも話しましたが、今は、次の世代のパイプ役として姉と2人でこの活動を引き受けました。子育て最中の会員もいます。なので「治らないんだったら遅らせる」という薬を作ってもらえたらありがたいです。近い将来、先生方のご尽力により、特効薬が誕生し、次世代の若者が希望に満ちた人生を送れることを切望しています。日々「去年できていたことが今年はできない。あれ?」という繰り返しです。「できたことができなくなる」というのを受け止めないといけないですね。受け止めていかないと前に進むことができないような気がします。受け止めきれない人はここで心を閉ざしてしまいますね。閉ざした心をどう開かせるかっていうのも、自分たちに課せられた仕事だと思っています。姉と2人でどこまでできるかわかりませんが、これからの人生の中で自分たち2人でできることはやっていきたいと思っています。
語者プロフィール
泉川 チズ子(いずみかわ ちずこ)さん
1955年 恩納村安冨祖出身
【趣味】フラワーアレンジメントハーモニカ
仲村 けい子(なかむら けいこ)さん
1957年 那覇市出身
【趣味】映画鑑賞
2025年7月の報告あれこれ
那覇看護専門学校実習
那覇看護専門学校3年生の地域在宅看護論としての実習を、アンビシャスは毎年受け入れています。難病支援における災害対策での電源確保については、在宅療養を担う看護師も電源の確保が出来ないと、患者さんへの支援が出来なくなるため実習内容に取り入れています。
また、コミュニケーション支援では、病気の進行や事故で発語が出来ない、筆談が出来ない場合に患者がご自身の意思を伝える方法についても説明し、実際に体験してもらっています(写真は透明文字盤を使用している様子)。
相談支援センターの業務の中心は、患者さんの話を聴くことです。同情・同感・共感の違い、ノンバーバル・コミュニケーションなどを説明した後ロールプレイをしてもらい、相手の良かった点、気になった点などを共有して傾聴スキルの向上をはかります。実習を受け入れる側も学びの多い機会となっています。
ALS協会沖縄県支部総会への参加
7月13日に北谷にらいセンターにおいてALS協会沖縄県支部総会が開催されました。活動報告・会計報告に続き、18年前に支部を立ち上げた経緯について説明があり、相互に助け合う貴重な会に成長していることが、支部長より話されました。その後、今困っていることを参加者間で話し、患者や家族、経験豊富な遺族、保健師やリハビリ職の支援者からの助言や共感がありました。最後に会員拡大や情報共有において、公式LINEを開設し発信する計画が提言されました。
7月のご寄付
7月は、多くの法人、個人の皆様よりご寄付をいただきました。詳細は11ページの上部に掲載させていただいております。また、おきぎんSmart募金から、定期的にご寄付としてお気持ちを寄せていただいている方々も数多くおいでになります。
アンビシャスの難病支援活動は、皆様からのご寄付によって成り立っており、寄り添っていただいているお気持ちは、大きな活動の励みになります。寄せていただいた大切なお気持ちに応えるべく今後も活動を継続して参ります。
保健所スケジュール
各保健所、今月の予定はございません。
【北部保健所】 Tel:0980-52-2704
【中部保健所】 Tel:098-938-9883
【南部保健所】 Tel:098-889-6945
【那覇市保健所】 Tel:098-853-7962
【宮古保健所】 Tel:0980-72-8447
【八重山保健所】 Tel:0980-82-3241
2025年度 難病医療相談会
難病の詳しい説明や治療・療養について、各疾患の専門医による個別相談を無料で受けることが出来ます。
※各疾患とも定員は4組です。定員を超えた場合はキャンセル待ちとさせていただきますのでご了承ください。
※予約時に相談員が相談内容や現在の治療についてお伺いします。おくすり手帳等を手元にまとめご連絡ください。
【疾患】神経系疾患/パーキンソン病・重症筋無力症・多発性硬化症・多系統萎縮症 など
【担当医】渡嘉敷 崇先生(沖縄病院)
【日程】10月10日(金)14時~16時
【開催場所】アンビシャス事務所(那覇市牧志3-24-29グレイスハイム喜納2-1階)
【相談方法】対面またはオンライン(Zoom)
2025「難病と診断されたときに役立つしおり」コラボ企画 難病勉強会・意見交換会
【日時】9月3日(水)14時~16時
【演題】国や都道府県の難病対策~難病診断後に役立つ制度やサービス~
【講師】沖縄県地域保健課疾病対策班 與那原 沙耶氏
【日時】9月24日(水)14時~16時
【演題】公認心理士の立場から~診断後の心と受容について~
【講師】臨床心理士(公認心理師)鎌田 依里先生
【日時】11月5日(水)14時~16時
【演題】病気になった時に役立つ社会保障~傷病手当金・失業保険・障害年金について~
【講師】社会保険労務士・行政書士オーシャン事務所 合同会社オーシャンオフィス大城代表 大城 恒彦先生
【日時】12月3日(水)14時~16時
【演題】難病とストレスのつきあい方~マインドフルネス瞑想を取り入れて~
【講師】沖縄国際大学総合文化学科 教授・公認心理師 上田 幸彦先生
【日時】1月14日(水)14時~16時
【演題】難病患者の働き方について~利用できる制度・職業訓練・企業側の声等~
【講師】難病患者就職サポーター 瑞慶覧 さつき氏
【日時】2月4日(水)14時~16時
【演題】難病のある人が治療と仕事を両立して働くには~難病患者に役立つ就労情報~
【講師】沖縄産業保健総合支援センター千葉 千尋氏
アンビシャスでは現在、「難病と診断されたときに役立つしおり」を製作しています。2025年は、ワークショップや勉強会、意見交換会を開催し、それぞれの内容をしおりに反映させ、オンライン上で公開予定です。しおりが「難病と診断された方々」に役立てられること、また、イベントを通じて参加者同士の繋がりが持てたり、知識を深めていただく機会となりましたら幸いです。
http://www.ambitious.or.jp/support/nanbyo_shiori/
【会場】沖縄県総合福祉センター東棟501教室(またはZoom)
【対象】難病患者様ご本人、ご家族、支援者、興味のある方
【お問合せ】沖縄県難病相談支援センター/認定NPO法人アンビシャス Tel:098-951-0567(平日10時~17時)
【申込み】こちらのフォームよりお申込みください。
こころの現場から
傷つきの連鎖を止める
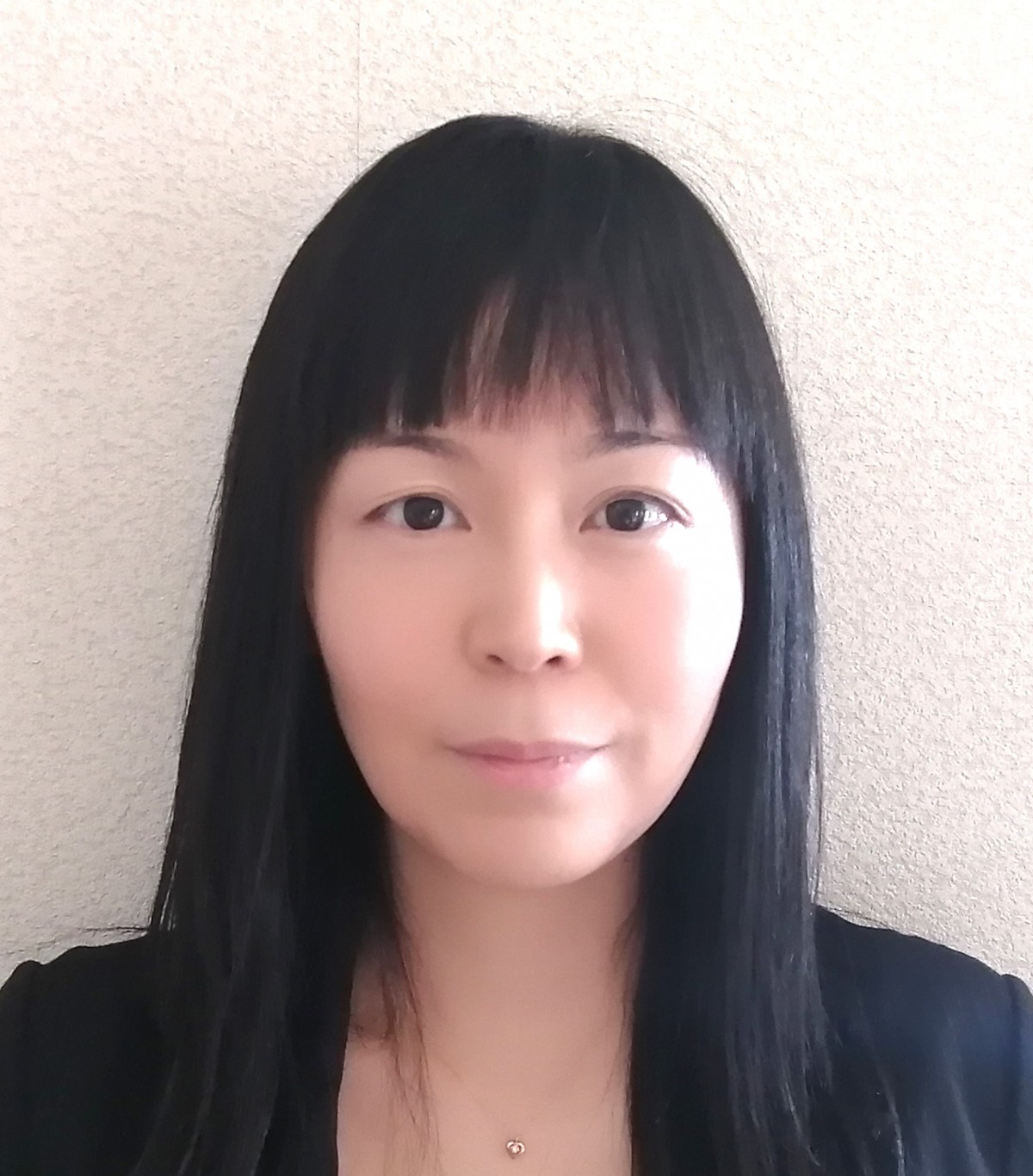
臨床心理士 鎌田 依里(かまだ えり)
皆さんは、親友や仲の良い友人はいますか。友人であれば「私たち友達だよね」なんて言葉は、こころが健康であれば言う必要はありません。「私たち友達だよね」という言葉が口をついて出ることは、自分と他者との関係性が構築されていることを実感できない不安があるからです。また、目に見えないことが信用できなく、形がないものは信用できないという傾向をもっているからです。それは幼少期からの重要な他者との信頼関係が構築される機会が少なかったことによる弊害で、人との信頼関係を結ぶことが困難なこころの弱さから生じるものです。
最近は、ソーシャルネットワーキング(SNS)で簡単に人と知り合うことができます。簡単に他者と繋がる方法の一つであるSNSでは、一時的な孤独感やさみしさを即座に紛らわすことが可能です。一方で、安易な関係をもって、傷つき、刹那的な対人関係を繰り返すことが多くなるというデメリットも有しています。
このような人を支援しようとするとき、必ずと言っていいほど支援者も傷つけられます。なぜかというと自分が傷つけられた経験がある人は、無意識に自分のこころの傷つきの大きさを知ってほしいがために相手も傷つけるからです。こころが傷ついている人を支援する対人援助職も、善意をもって支援しているのにもかかわらずその善意を信じてもらえずに傷つけられるのです。
人はお互い理解しあうためには言葉だけでは足りません。直接、相手の顔を見て、自分の気持ちを話すだけではなく、ともに時間をすごすことによって、相手の言葉だけではなくその場で醸し出す空気感や言外の想い等も感じ取ることができます。傷つきの連鎖は、皆さん自身で止められるといいですね。
つぶやきチャンプルー
後悔の先に立つために必要なこと

著:照喜名通
人は「楽観バイアス」といって、何らかのアクシデントが自分の身には起きないはずだと楽観的に考えています。常に悲観的であると身も心も参ってしまいますので、楽観的に受け止めることを選択します。
しかし、医師から難病と診断され、この病気は原因が判らず、進行を抑える薬はあるが、完治することはなく、長期的に治療が必要と言われると楽観的ではいられなくなります。最近、保健所の保健師さんと筋萎縮性側索硬化症の患者さん宅を訪問させていただく機会が多くなっています。
特にACP(アドバンス・ケア・プランニング)といって日本語では人生会議と意訳され、今後ご自身の病状が進行して介護が必要になったり、意識が無くなった場合などに、どのような医療やケアを受けたいのかを、前もって本人・家族、また医療・ケアチームと共有する作業をさします。本人の希望にそった対応をすることで、本人と残された家族の後悔が軽減されます。
日本も含め世界的にACPの取り組みを推奨する傾向にあります。人工呼吸器つける?延命処置は?と聞くのは「なに、そんな縁起でもない」と言って対話が進まなくなってしまいます。楽しみなのは何か、生き甲斐は何か、許せないことは何かなどだけでも聞き、その人の価値観、人生観を対話の中から拾い上げて話しあっておくことで、患者本人も家族も納得でき後悔することが少なくなると思います。あなたはどう生きたいですか?
シリーズ 「患者学」第125回
エンパワーメントの医療(前篇)
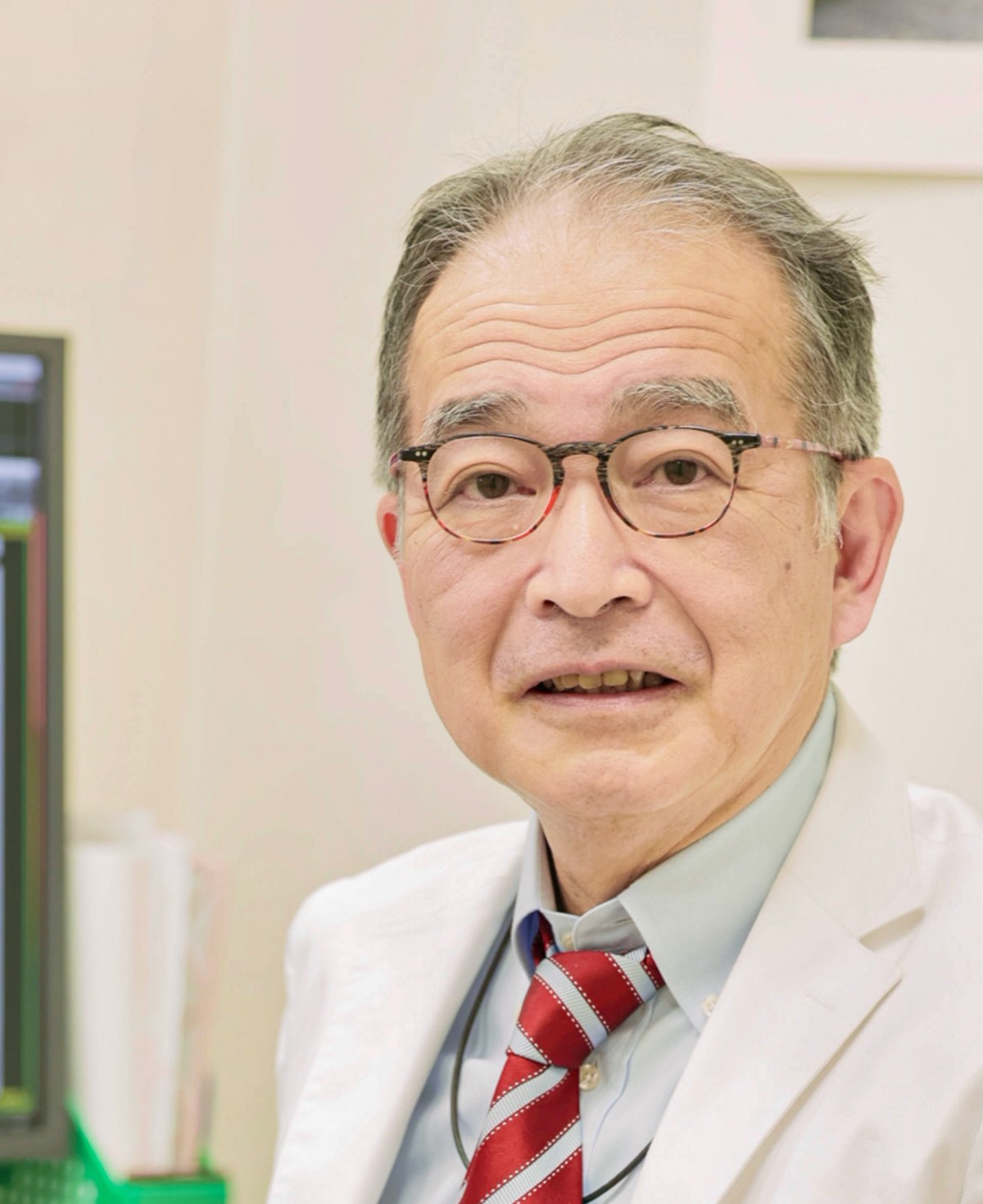
慶應義塾大学 名誉教授 加藤 眞三著
エンパワーメントの医療への転換
患者学で目指している「真の意味で患者中心の医療」を実現するためには、医療者が患者を管理するのではなく、患者のパートナーになることが求められます。そのためには、患者の自律心を解放することでセルフマネジメントをうながし、患者さんの持つ潜在能力を発揮させること、すなわちエンパワーメントが必要となります。
このようなエンパワーメントの医療は1990年代に糖尿病のケアから生まれてきました。従来の医療のやり方では、糖尿病のコントロールが上手くいかなかったことに対する反省から生まれてきたのです。今回は、特に慢性病において必要とされると考えられるエンパワーメントの医療について説明します。
糖尿病におけるセルフマネジメントの必要性
糖尿病患者の数は近年全世界的に大きく増加してきました。その背景には、現代社会における生活習慣の変化があります。食事で摂取する脂質や単純糖質の増加、早食い、運動の不足、ストレス、睡眠不足などが重なり肥満が増加してきたからです。そのために、糖尿病の治療では、生活習慣の是正が何よりも本質的であり重要です。生活習慣を変えるためには、患者自身によるセルフマネジメントが必須であり、患者自身がやる気をおこし、主体的に治療に取り組むことが望まれます。
しかし、従来の医療では、経口薬による治療やインスリン注射などの薬物療法が主体であり、患者教育においても、病気や治療についての知識の提供に重点が置かれていました。しかし、教育された知識が日常生活でどのように実践されるかは、患者側の問題として放任されていたのです。あるいは、教育の後でも結果が悪いときには、脅しの医療が行われていました。
つまり「医療者は患者に医学上の知識を授け、患者はその知識に従った生活をする。医療者は患者に薬を処方し、患者は規則正しく服薬することが求められる。医療者は患者を管理し、患者は医療者に管理される立場にある」という考え方が、支配的だったのです。
このような医療者側の態度が患者に不満を生じさせ、患者と医療者の関係性の破綻を招く結果になっていました。そして、そのことが糖尿病のコントロールをさらに悪くしていたのです。
エンパワーメントの医療
このような状況が続いていた中で、新たな医療として提唱されたのがエンパワーメントです。「患者は医療者の指示を守るだけの受動的な人」として扱うのではなく「糖尿病は患者のものであり、患者自身が問題を解決し、対処していく能力をもっている」ことを前提とする医療です。つまり、患者の主体性を重んじる医療なのです。
医療者は糖尿病の専門家として患者を支援しますが、一方で、患者も自分の人生を生きることにおける専門家であり、糖尿病をもちながら生きる自分の人生の専門家でもあるのです。医療者と患者がそれぞれの専門家として、お互いに対等な立場のパートナーとして協働作業することで、糖尿病問題の解決を目指そうとするのがエンパワーメント型医療だったのです。
しかし、このような変化が必要とされるのは、糖尿病の医療にとどまりません。他の生活習慣病で必要とされることはもちろんですが、他の慢性病や難病においてもこのような転換が必要とされているのです。
次号に続く
- 慶応義塾大学看護医療学部
名誉教授 加藤 眞三 - 慶應義塾大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所研究員。
患者と医療者の協働関係を作り上げることをテーマに公開講座「患者学」や著作 等を通じ、患者も自ら積極的に医療に参加する啓発活動に取り組む。
加藤先生の YouTube配信中です!
「Dr.シンゾウの市民のための健幸教室」
加藤先生の最新書籍:いのちをケアする医療
出版社:春秋社
患者団体からのおたより
沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄)より
防災学習会&交流会のご案内
今回、下記の要領で防災士・防災危機管理者で災害福祉支援チームDWAPおきなわのメンバーの方に防災についてご講演をいただき、参加者を含めて意見交換したいと思います。
併せて防災グッズの展示も行います。
防災学習会の後は、交流会とiPhone勉強会も開催予定です。
【日時】令和7年9月28日(日)13時~16時
【場所】那覇市障がい者福祉センター 那覇市古島2丁目14-4
【スケジュール】
▶13時から15時 防災学習会
演題:自分を守る知恵と力~日常生活の延長にある防災!みんなは何から始めてる?~
▶15時から16時 交流会
おしゃべりや情報交換をしませんか。iPhoneの個別相談もできます。
【定員】30名
【申込期間】9月8日(月)~12日(金)
【申込・お問合せ】080-1723-8871(小野)
「表紙は語る」体験談募集!
当誌では毎月いろんな方にご自身の病気に関する体験談を「表紙は語る」と題して掲載しています。
あなたのご体験を当誌面に掲載してみませんか。
表現は基本的に自由です。但し特定の宗教や政党、サプリメントの紹介等はご遠慮願います。
文章を書くのが苦手な方でもアンビシャスがお手伝いします。
お気軽にお申込みください。
文字数は2,000~2,200文字 400字詰め原稿用紙5枚程度
ご執筆料として 11,137円(源泉徴収額:1,137円含む)を進呈します。
ご希望の方はアンビシャスまで
Tel:098-951-0567
メール:info@ambitious.or.jp
今月のおくすり箱
抗生物質服用時の整腸剤使用について

沖縄県薬剤師会 白坂 亮
医薬品には様々な菌に対応できるよう多くの種類の抗生物質があります。菌の種類や用途に応じて医師が抗生物質を処方しますが、その際に整腸剤も一緒に処方される場合があります。
その理由としては、抗生物質の影響により腸内細菌のバランスが崩れ、下痢などを起こすことがあるためです。抗生剤と一緒に処方される整腸剤の一つとして「ビオフェルミンR錠」があります。ビオフェルミンR錠の「R」は耐性を意味する英語の頭文字を取ったものです。このビオフェルミンR錠は抗生物質に耐性をもつため、抗生物質を使用中でもビオフェルミン由来の乳酸菌が影響を受けにくいという特徴があります。
お薬を服用中に、本来の病気とは関係のない症状が出てしまうと、治療の中断につながってしまうきっかけにもなります。もし、抗生物質を服用した後にお腹の調子が悪くなった経験がある方は、その旨を主治医にお伝えください。
なお、抗生物質の種類や投与期間、個人の体質などによって程度は異なります。整腸剤の必要性も個々のケースによって判断されますので、気になる方はお近くの医師や薬剤師にご相談ください。
アンビシャス広場
~エッセイ~ 「入院」 眞榮田 純義さん(ALS)
先日、胃瘻造設術で入院して以来一年ぶりに入院しました。
今回の入院の目的は、非侵襲的陽圧換気(NPPV)を導入することが決まりその練習目的で入院していました。手や足の動きがなかなか自由にならない今、電話をする際はスピーカーで話すしかなく、持参したiPadで映画などを見る際にイヤホンを自分で耳に装着することもできないため、大部屋だと周りの方への迷惑や入院療養上不便なことが多いと考え個室に入院しました。
そしていよいよNPPVの練習が始まり、まずは日中どれぐらいつけることができるか試しで付けてみることにしました。付け始めの5分ぐらいはNPPVから出てくる空気と自分自身の呼吸を合わせることがむずかしかったが、少しずつタイミングがあってくると特段違和感なくつけることができた。日中初めてつけた時間は約3時間装着でき、そのまま夜就寝の際にも装着して就寝し、朝起床の際までそのままつけることができました。看護師や主治医などからは「初日からこんなに使える人はあんまりいない」と驚かれていました。予定より早くNPPVに慣れることができたので、一日前倒しで退院し今は寝る前の相棒としてNPPVを使っています。
お勧め映画/DVD情報
1)丘の上の本屋さん 2021年
イタリアの丘の上の小さな古書店の店主と、移民の少年が、本を通して交流をしていく。
2)フラッグ・デイ 父を想う日 2021年
愛する父が実は犯罪者だったと知った娘が葛藤をしながら向き合って行く実話を元にした作品。ショーン・ペンが実娘ディラン・ペンと共演。
3)MUD -マッド- 2012年
少年2人が無人島で出会った謎めいた男。彼は良い人か悪い人か、なぜ無人島に居るのか。青春映画とサスペンスを足したような良作。
4)28DAYS(デイズ) 2000年
アルコールと鎮痛剤の依存症の女性が、問題を起こしまくり、更生施設で28日間のリハビリを行う。依存症は、人間関係や信頼を無くす…。
★渡久地 優子{進行性骨化性線維異形成症(FOP)}★
今月の占い
- 牡羊座 3/21-4/19
身の回りを綺麗に
☆リフレッシュ法:断捨離 - 牡牛座 4/20-5/20
休息は小まめに
☆リフレッシュ法:仮眠 - 双子座 5/21-6/21
助言に聞く耳を
☆リフレッシュ法:読書 - 蟹座 6/22-7/22
充分な栄養管理を
☆リフレッシュ法:飲食 - 獅子座 7/23-8/22
お洒落して気分転換
☆リフレッシュ法:スキンケア - 乙女座 8/23-9/22
笑顔や挨拶を忘れずに
☆リフレッシュ法:散歩 - 天秤座 9/23-10/23
無理に頑張り過ぎずに
☆リフレッシュ法:お風呂 - 蠍座 10/24-11/21
疲れない程度で
☆リフレッシュ法:歌唱 - 射手座 11/22-12/21
自分の時間を充実に
☆リフレッシュ法:DVD・TV鑑賞 - 山羊座 12/22-1/19
人にも自分にも優しく
☆リフレッシュ法:音楽鑑賞 - 水瓶座 1/20-2/18
言葉遣いを丁寧に
☆リフレッシュ法:ネット観覧 - 魚座 2/19-3/20
ポジティブ思考で
☆リフレッシュ法:談笑
編集後記
今月の「表紙は語る」にご寄稿いただいたのは、沖縄型神経原性筋萎縮症を抱えている泉川チズ子さんと仲村けい子さん姉妹の体験談です。ご自身の病気のリハビリや治療をうけながら患者会を引き継ぎ、運営面にも尽力し、また多くの医師とつながり創薬を視野に入れた研究に協力されている姿に深い感銘をうけました。アンビシャスとしても広報などの支援をさせていただきたいです。皆さまも暖かいご支援をお願いいたします。
アンビシャスの事業として、8月から難病医療相談会も始まっています。9月には難病勉強会も2回計画をしていて、10月を除く来年の2月まで、毎月開催しています。会報誌または、ホームページ、公式LINEのイベント情報をご参照ください。
体験談の感想や会報誌、ホームページなどの広報についても、分かりにくい点やご意見ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今のところ大きな台風は沖縄には接近していないのですが、他県では猛暑、豪雨などの災害が起きています。備えは常にしておきましょう。暦の上では秋ですが、沖縄での残暑は続きます。引き続き残暑お見舞い申し上げます。
文 照喜名 通
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.